 
| 天野 浩 |
 |
|
 |
 |
 |
|
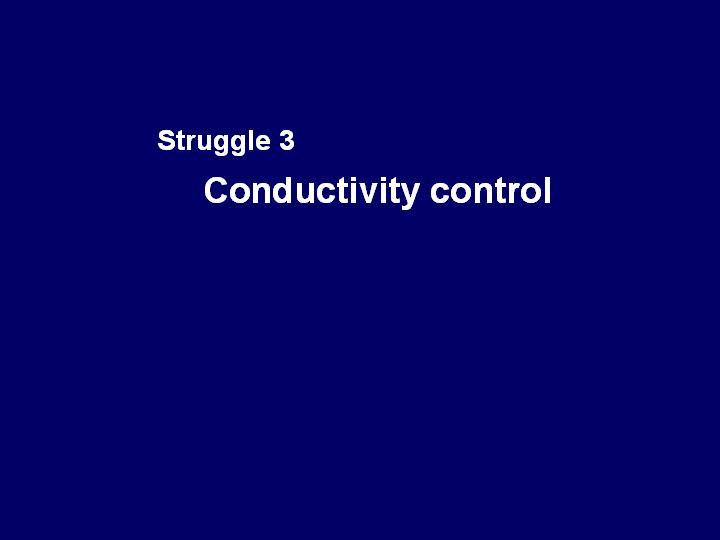
[図 16]

[図 17]

[図 18]

[図 19]

[図 20]

[図 21]
|
[図 16]
当時、ガリウムナイトライドは、ある人によれば、p型結晶は絶対できない結晶だ、というようなことを言われていた時代だったわけです。そのような困難を乗り越えるキッカケは、やはり、ある偶然によって生まれました。
[図 17]
当時、ドクターコースにいっていた私は、インターンシップで、NTTの武蔵野通研にお世話になっておりました。その時やっていた仕事が、カソードルミネッセンスの評価というもので、これがその装置です。その実験をしていると、非常に奇妙な現象に出会ったわけです。
[図 18]
亜鉛をドープしたガリウムナイトライドのカソードルミネッセンスを見ていると、見れば見るほど、どんどん明るくなってくる。これは不思議だと思ってデータを取ったものがこれです。カソードルミネッセンスというのは、電子線を当てて試料を励起して発光する、テレビのブラウン管と同じような原理です。ですので、電子線を当てることによって、亜鉛をドープしたガリウムナイトライドが、ものが変わるということを表しています。
[図 19]
これはおもしろいと思って、電気的な評価も行いましたが、その時には、p型結晶を作ることはできませんでした。やっぱりダメか、この結晶はp型はできないんだ、とあきらめかけていた時に、あるテキスト、教科書に出会いました。フィリップスという人が書いた「半導体結合論」というのをパラパラとめくっていて、たまたま目に留まった絵がこれです。
この絵は、その時通常使っていた亜鉛という不純物に比べると、マグネシウムは、アクセプタといってp型になりやすい元素だということを表した絵です。これは、と思いまして、さっそく、亜鉛からマグネシウムに原料を変えました。マグネシウムに変えただけでは、p型にできなかったんですが、それにさらに先ほどの電子線を照射することによって初めてp型の結晶ができるようになったわけです。
[図 20]
当時は、現在のようにプロセスの技術も進んでいませんので、電極の取り方も非常に初歩的なものしかできませんでした。pn接合にしては、電圧がちょっと高いということで、色々おっしゃる方もおられたんですが、私は非常に自信を持っていたわけです。というのは、ホール効果で測ると間違いなくp型だというのがわかっていたからです。
[図 21]
これは、電子線照射を利用してパターンを描いた例です。これは、Mという字を、電子線照射してその部分だけp型にして作った発光ダイオードです。これは、レーザというのは部分的なところに電流を集中しなければいけないので、ストライプの部分だけp型にして作ったレーザのパターンです。
|
|
|