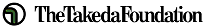
年度計画・報告 Annual Report
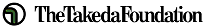
年度計画・報告 Annual Report
平成18年度 事業計画書
(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)
1. 顕彰事業
平成17年度に引き続いて、日本のバイオベンチャーを応援するバイオビジネスコンペに「バイオ先端知賞」(賞金100万円)を提供する。平成18年度の最終審査は、2007年4月に行われる予定である。賞金については、主催団体であるバイオビジネスコンペJAPAN実行委員会 事務局(大阪商工会議所 経済産業部内)に平成18年度中に振り込む予定である。
2. 助成事業
若手優秀研究者1名に武田奨学賞を授与する。期間は1年間で金額は100万円とする。選考は推薦によって幹部会で行い、理事会で承認する。
3. 調査事業
(1) 事例調査
① アントレプレナー列伝「超波及度編
平成17年度の事業として調査を行ったが、追加調査とまとめが必要であり、これを行い調査として完結させる。調査対象とするのは、以下の10名である。
Linux: Linus Torvalds
GNU: Richard Stallman
セルプロセッサ:久多良木 健
iモード: 榎啓一
2足歩行ロボット:広瀬真人
ロボットパロ:柴田崇徳
カーボン・ナノチューブ: 飯島澄男
SiC: 松波弘之
HEMT: 三村高志
ZnO: 川崎雅司
② 世界をリードした半導体共同研究プロジェクトの調査
最近の半導体関係の共同研究プロジェクトは、洋の東西を問わず、複数の会社からの出向者を集めたものが多く、それがほぼ常識化されて来ている。このような共同研究の源泉をたどると1975年から1980年に行われた通産プロジェクトの超LSI共同研究所に行き着く。超LSI共同研究所は世界初の新しい手法の開発ということから、アントレプレナーシップの発揮と言えよう。さらに、超LSI共同研究所の試みは、欧米に於ける研究にも影響を与え、米国におけるSEMATIC、欧州に於けるIMECなどの世界の共同研究の潮流となった。
この調査では、原点に戻って、超LSI共同研究所とそれ以降の主な共同研究プロジェクトをレビューし、超LSI共同研究所において掲げられた"基礎的共通的"な考え方の与えた効果を考え、それがその後の共同研究にどのように生かされて来たか、生かされていないかを調べ、今後のプロジェクトの参考に供したい。日本のみならず、米国や欧州の共同プロジェクトについても調査を行う。(添付資料参照)
(2) TTM
財団スタッフの勉強会として、毎週1回火曜日に実施する。自分が関心をもったテーマについて説明し、全員で討論を行う。財団の活動方針や、武田シンポジウムなど財団行事の企画についてもこのミーティングで討論する。
また、外部講師の依頼も計画する。
(3) 委託調査
これまで蓄積した財団スタッフの調査能力を生かし、さらに磨くために産総研などから調査の依頼があった場合には積極的に受託する。
4. 普及事業
(1) 武田シンポジウム
武田計測先端知財団主催により2007年2月(予定)に東京大学武田先端知ビル武田ホールで実施する。財団理念に基づくメッセージ発信の場とする。
(2) カフェ・デ・サイエンス
今年度もカフェデサイエンスを実施する。「普通の人たちが、専門用語で独特の概念について議論することになれてしまっている科学者と一緒に、日常的な言葉と具体的なイメージで科学を語り、それによって、科学の知識を得ようというのではなく、物事を科学的に考えるとは、どういうことなのかを体得する場とする。」ことを基本的な考え方とすることは継続する。
テーマ、会場については、事務局と中心として検討し実施する。年6回程度の開催を予定するが、個別のテーマを設定したものも、場合によっては追加開催する。
また、日本学術会議の呼びかけにより、2006年4月の科学技術週間に、全国各地でサイエンスカフェを行うことになった。その実行の責任部署の(財)科学技術広報財団 日本科学未来館運営局より、武田計測先端知財団にも協力依頼があった。2006年4月21日と22日に福井市で財団が主催してカフェデサイエンスを開催する予定である。経費は、(財)科学技術広報財団が負担する。講師は、斎藤 成也さん(国立遺伝学研究所 集団遺伝研究部門 教授)と佐々木 閑さん(花園大学文学部仏教学科教授)にお願いした。
(3) 広報・出版
① 出版
アントレプレナー列伝「超波及度編」
平成17年度の調査事業として行った、アントレプレナー列伝「超波及度」編について、必要に応じて追加調査を行い、単行本として刊行する。
プロシーディングスの刊行
武田シンポジウム2006の講演録、2005年調査事業及び普及事業概要を掲載した「2005年武田計測先端知財団プロシーディングス」を刊行する。
調査結果をもとにした本の刊行
産総研から平成17年度の委託調査事業として行った、「先端技術の資源制約に関する調査」、「企業の持続的発展可能な社会実現への取り組みに関する事例調査」をもとにした本の刊行を検討する。
②財団ホームページ更新
カフェデサイエンスの内容、TTMの概要、武田シンポジウム2007の内容を掲載したホームページの更新行う。
5. 総務関係
(1) 財団事務所について
聖路加タワー31階の現在の財団事務所の賃貸契約は2006年3月で契約期間が満了する。その後の財団事務所については、財団運営上の利便性と財団財政事情を考慮し、現在の31階事務所の賃貸契約を2年間(2006年4月から2008年3月まで)延長する。賃貸料は、相場としては上昇傾向にあるが、ビル側との交渉の結果、月額賃貸料を2.5%減額し、共益費を含めて月額99万4780円で合意している。
(2) 会計監査契約の会計コンサルティング契約への変更
これまで新日本監査法人に監査を依頼してきた。
これは、設立当時の収支決算額が、10億円を超えていたため、平成13年2月9日付けの「公益法人の指導監督体制の充実等について」 (公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)において、「各府省は、資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上の所管公益法人に対し、公認会計士等による監査を受けるよう要請する。」に基づいていたものである。その後も、監査法人による監査を受けておいた方が望ましいと考え、監査法人の監査を継続してきた。
しかし、平成17年度末において、財団資産額が4億円以下、収支決算額は1億円以下になっており、資産額、負債額、収支決算額のいずれにおいても、上記条件に当てはまらないので、新日本監査法人との契約を監査契約から、コンサルティング契約に変更する。決算書類の作成などは、今までどおり行ってもらうが、監査法人としての監査報告はなくなる。財団監事に決算の監査をお願いし、理事会と評議員会で承認を頂く。
添付資料
世界をリードした半導体共同研究プロジェクト
垂井
超LSI共同研に始まる例
最近、半導体関係の共同研究プロジェクトといえば洋の東西を問わず、複数の会社からの出向者を集めたものが多く、それがほぼ常識化されて来ている。これは他の産業ではあまり見られないものである。このような共同研究の源泉をたどると、1975-1980年に行われた通産プロジェクトの超LSI共同研究所(*1)に行き着く。
超LSI共同研究所は国内コンピュータメーカー5社からの100名を超える出向者を一箇所に集めて、4年余のあいだ研究を行ったもので、ライバルメーカーからこれだけの人数と期間を集めたということで、世界的にも初めての試みであるのみならず、その成果についても評価は高く、80年代の日本半導体躍進をもたらした要因の一つと評価されている。世界初の新しい手法の開発という事から、アントレプレナーシップの発揮と云えよう。さらには生活者の立場から云えば役にたつ結果を生みだしたかどうかが重要となる。
超LSI研の成功は欧米に於ける研究にも影響を与え、米国に於けるSEMATIC,欧州に於けるIMECなどの世界の共同研究の潮流となった。
一方、日本国内に於いては米国とのIC摩擦を恐れて、超LSI共同研の後、しばらくこの分野の共同研究は差し控えられた。再び復活が可能となったのは、日本に対する米国の優位が明らかになった1996年頃であり、ASET、Selete、Super Siなどが一斉にスタートした。
この間20年に近い空白と、日米IC摩擦による強制的な20%の輸入品買い上げなどによって、日本半導体産業は米国に比較して弱められたのみならず、その間アジア諸国の急速な発展を生じさせる事となった。この様な客観情勢も加わってか、1996年以降再開された各種のプロジェクトも、日本半導体産業の復活にはそれ程めざましい効果を上げている様には見えない。たとえば、多彩な経歴をお持ちの小宮啓義氏の著書(*2)から関係する文を以下に引用させて頂く。
「日本では、超エル‐エス‐アイプロジェクト後に実施された、あるいは実施中の半導体関連の国家プロジェクトが産業競争力強化という視点で見ると、ほとんど見るべき成果を出していないというのは、残念ながら周知の事実である。」
本書はここで原点に戻って、超LSI共同研究所とそれ以降の主なる共同研究プロジェクトをレビユーし、超LSI共同研究所において掲げられた"基礎的共通的"な考え方の与えた効果を考え、それがその後の共同研究にどのように生かされて来たか、生かされていないかを調べ、今後のプロジェクトへの参考に供するものである。
(*1) 正式名称は超エル・エスーアイ技術共同研究組合共同研究所であるが、長いので略記させていただく。
(*2) 小宮啓義著;日本半導体産業の課題、電子ジャーナル社 2004、P128